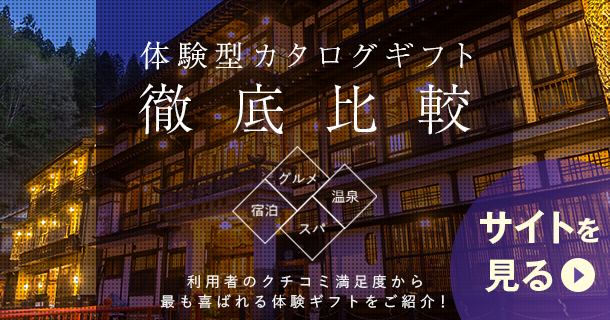慶事?弔事?シーン別ギフトのラッピング方法
贈り物をするときには、ラッピングをする機会も多いことでしょう。ギフト専門店で購入した場合には、マナーを熟知しているため、ラッピングや熨斗(のし)紙についても、「ほぼお任せ」でOKでしょう。一方で、「用途に合わせたラッピング方法」を自分自身で行う機会は、そう多くないかもしれません。
いざ自分でラッピングを行おう!と思ったときには、マナーにのっとったラッピング方法を踏まえた上で、行う必要があります。そこで、ラッピングに関する具体的なマナー、シーン別の注意点について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
慶事の場合のラッピング方法

まずは何かおめでたいことがあったときの慶事用ラッピング方法から紹介していきます。結婚祝いや出産祝い、昇進祝いや快気祝いなど……贈り物をする機会は多いものです。喜ばしい出来事に対して、それをお祝いするギフトを選ぶのは、贈り手にとっても幸せなことだと言えるでしょう。
相手のことを思い、自分自身でギフトの品物を用意したときには、以下の手順に従って包んでみてください。一般的な「キャラメル包み」の方法について、解説します。
- 1.包装紙の上に品物を、裏面を上にしておく
- 2.向かって右側の紙を中央付近に合わせるようにして、品物の位置を調整する
- 3.いったん右側の紙を元にもどし、左側の紙→右側の紙の順番で、中央に向けて折って重ねる
- 4.テープで重ねた部分を留める
- 5.閉じ口に、丁寧に折り線をつける
- 6.上下をしっかりと折りこんで、テープで留める
慶事のラッピングの基本は、3の手順で包装紙を合わせる部分で、左側よりも右側が上に来るようにすることです。ラッピングの上から熨斗紙をかける場合には、ラッピングの向きに注意しましょう。いったんその場を離れ、反対向きで熨斗紙をかけてしまうと、せっかくのラッピングが無駄になってしまいます。
また、慶事においては、喜び事が重なるよう包装紙を2枚重ねてラッピングをするようなケースも少なくありません。こちらについても、ぜひ意識してみてください。
慶事におけるギフトは、相手に対して「おめでとうございます」の気持ちを伝えてくれるものとなります。心を込めることはもちろんですが、マナーを守ってラッピングを行うことが重要です。ラッピングをする際に、慶事・弔事のマナーを理解しないまま適当に包んでしまうと、「慶事にもかかわらず、弔事用のラッピングスタイルだった!」なんて失敗にもつながりかねません。
ギフトを受け取る側としては、なんとなくお祝い事に水を差されたような気分になってしまうもの。特に注意して、包装紙の右と左が逆にならないよう、注意しましょう。
また、弔事以外のギフトは、慶事のラッピング方法を採用するのが基本です。さまざまなギフトのシチュエーションで活用できる基本の方法なので、まずはしっかりと頭に入れておいてください。
弔事の場合は慶事とは逆が基本

日本においては、弔事の際にギフトを用意するケースも少なくありません。亡くなった方やご遺族に対する気持ちを、ギフトに込めて持参することもあるでしょう。弔事には、弔事にふさわしいラッピングをすることが大切です。
弔事のラッピングの手順は、基本的に「慶事の逆」と考えてください。つまり、先ほどのポイントにあった3の手順において、右よりも左が上に来るよう、注意しながら折ることになります。
また「デパート包み」とも呼ばれる「斜め包み」においては、「悲しみが早く流れますように」という意味を込めて、ポケットは下にあり、またラッピング用紙の合わせ目も下に向かうように整えられています。
こちらも、慶事の場合とは逆になるので、忘れないようにしましょう。
弔事の場合には、ラッピング方法を間違えたとしても「突然のことで、きっと慌てていたのだろう」と思ってもらえる可能性もあります。とはいえギフトを受け取る側の気持ちを考えると、シーン別に、きちんとしたマナーにのっとったラッピングを実践したいところです。
弔事のギフトにおいて、慶事とは逆の包み方をすることがマナーとされているのは、「非日常的な出来事であるため」だとされています。弔事が「日常」であっては困る、との考え方から、このようなマナーが生まれているのですね。
また慶事においては、包装紙を2枚重ねにして使うケースも多いですが、弔事の場合には「1枚のみ」でラッピングをします。弔事の場合には「不幸が何度も重なることがないように」という思いから、ラッピング用紙を重ねないようにしてください。
弔事の場合にも、熨斗紙を掛けるケースは多いものです。慶事のときと同じく、品物の上下を間違えないようにして、準備を行ってください。熨斗紙を掛けるまでに時間が経過してしまい、どちらが上なのか忘れてしまったときには、必ず裏の紙が重なっている部分を確認するようにします。
日常的な贈り物はTPOに合わせたラッピングを

慶事や弔事だけではなく、日本には「あらたまってギフトを贈る機会」というものが多くあります。このようなきちんとした場所においては、シーン別のラッピングのマナー、熨斗紙のマナーにまで気を配って、相手に対して失礼のないよう、意識しましょう。
とはいえ日常生活について考えてみると、こうしたギフト以外にもさまざまなギフトが存在しています。
- ・「お疲れさま」の気持ちを込めた、「ねぎらい」のギフト
- ・「ありがとう」の気持ちを込めた、「感謝」のギフト
- ・子どもの入園や入学に向けた、「おめでとう」のギフト
これらのギフトは、個人的にやりとりをするものであって、画一的なマナーを守るよりも、「相手のことを考え、喜んでもらえるラッピングをする」というのが、オススメの方法です。
季節感あふれるラッピング用紙を使ったり、華やかなアレンジを楽しんだりするのも良いでしょう。包み方に工夫すれば、見た目にも華やかな特別なギフトが出来上がります。ギフトそのものだけではなく、ラッピングから「相手を思いやる気持ち」が伝わるとしたら、それはとても素晴らしいことだと言えるでしょう。
カタログギフトなどは、どのような贈り物としても活用しやすいものです。価格帯もさまざまですから、「あらたまった場所できちんとしたギフト」以外にも選びやすいと言えるでしょう。自分でカタログギフトを用意したら、ぜひ「相手を喜ばせるラッピング」についても、検討してみてください。
相手の好みや状況、時期などにもしっかりと配慮することで、心のこもった贈り物を実践できることでしょう。
ラッピングにも心を込めて
ギフトの世界は、非常に奥が深い世界です。普段あまり意識しないような、さまざまなマナーやルールも存在しています。特にギフトのラッピングについては、「買い物をしたお店にお任せしてしまう」という方も多いはずです。そもそも「ラッピングに、慶事・弔事の違いがあることを知らなかった!」なんて方もいるかもしれませんね。
ラッピングはギフトそのものを包み、丁寧な印象に仕上げてくれるものであると共に、第一印象で相手への「気持ち」を伝えてくれるものでもあります。マナーにのっとったラッピングを実践することで、相手を不快にさせることもなくなるでしょう。
あらたまった場所以外では、あえて「かわいらしさ」や「華やかさ」にこだわったラッピングを行った方が喜ばれるケースも少なくありません。こうした意味では、「どんなラッピングをしようかな?」と考えることも、「相手に対する気遣いであり、贈り物をする醍醐味」と言えるのかもしれませんね。
値段の幅が広く、また相手に好きなものを選んでもらえるカタログギフトは「手軽なギフト」としてさまざまな場所で選ばれています。ギフト選びにあまり時間をかけられないときでも、安心して選ぶことができるでしょう。とはいえ「カタログギフトだと、華やかさやオリジナリティーが足りない」と感じる方もいるのではないでしょうか。
このような場合には、ぜひラッピングにこだわってみてください。慶事・弔事用のラッピングマナーはもちろんのこと、「相手に喜んでもらえるラッピングを」という視点で準備を行うことで、ギフトの特別感もぐんと高まることでしょう。