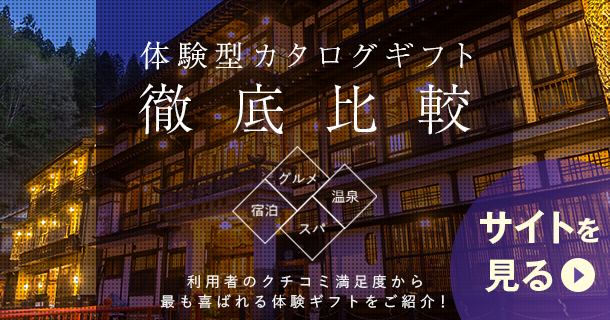寒中見舞い・余寒見舞いのマナーとは?
冬の始まりと共に、気にかけておきたいのが「寒い時期に送る季節の挨拶状」についてです。寒中見舞いや余寒見舞いがこれに当たりますが、相手の体調を気遣うと共に、自身の近況を伝えることで、大人のコミュニケーションを楽しむことができます。
とはいえ、日本に古くから伝わる大切な風習だからこそ、「マナーを守って行う」ことが重要なポイントとなります。失礼のない寒中見舞いや余寒見舞いの出し方・書き方について解説します。
はがきだけではなく、ギフトで気持ちを伝えたいと思うときの予算の相場や、品物選びのコツについても紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
寒中見舞い・余寒見舞いはいつ出す?

まずは寒中見舞い・余寒見舞いそれぞれの、基本的な情報について紹介します。
寒中見舞いは、一年の中でも、もっとも寒さが厳しい時期に出す挨拶状です。1月7日頃から2月4日頃までを目安に出すことをオススメします。
なぜこの時期なのかというと、1月7日までは松の内で、季節の挨拶状としては「年賀状」を使うのが一般的です。そして2月の上旬には立春を迎え、暦の上では「春」となります。この間の時期に送付するのが、寒中見舞いとなります。
年賀状から時間をおかない挨拶状ということもあり、寒中見舞いは以下のような目的で出されるケースも少なくありません。
- ・喪中の方への、年賀状代わりの挨拶状として
- ・喪中と知らずに年賀状を出してしまった際の、お詫びの手紙として
- ・喪中と知らずに年賀状をいただいた場合の、返信として
- ・年賀状をいただいていたにも関わらず、返事が遅れてしまった際の挨拶状として
- ・喪中はがきが間に合わなかった場合の、挨拶状として
もちろんこのほかにも、シンプルに季節の挨拶状として活用する方も少なくありません。
ただし寒中見舞いの場合は、年賀状との兼ね合いから、「普段ははがきで季節の挨拶を行わない」という場合でも活用する機会が多いという特徴があります。相手に対する気遣いの手紙だからこそ、マナーを守って実践してみてください。
さて、一方余寒見舞いのはがきは、立春を過ぎたあとに使います。2月末まで、もしくは3月上旬までの厳しい寒さの時期に出すようにしましょう。
先ほど挙げた理由で寒中見舞いを出そうと思っていたにも関わらず、立春を過ぎてしまった場合には余寒見舞いとして対応します。
基本の書き方

では実際に、寒中見舞いや余寒見舞いはどのように書くべきものなのでしょうか。「どう書けば良いのかわからない」というときには、以下の例を参考にしてみてください。
1.寒中見舞い申し上げます(余寒見舞い申し上げます)
はがきの右上から、「寒中お見舞い申し上げます」もしくは「余寒お見舞い申し上げます」と記載します。はがきを出した目的を伝える一文ですから、やや大きめに書くことを意識してください。
2.時候の挨拶
次は時候の挨拶を添えます。寒中見舞いに使える挨拶としては「松の内の賑わいも過ぎ」や「雪の舞う寒さ厳しい今日この頃」などが挙げられます。余寒見舞いの場合は「余寒厳しき折柄」や「雪解けの水もようやくぬるみ」などのフレーズが使えます。
ただし時候の挨拶は省略されるケースもあり、また相手が喪中の場合にはおめでたい言葉を使うのは避ける必要があります。
3.年賀状に対するお礼やお詫び
年賀状をいただいた相手に対してはお礼の気持ちを、そして何らかの理由により出せなかった相手にはお詫びの言葉を伝えます。
4.相手の近況を尋ねる
寒中見舞いや余寒見舞いは、寒さが厳しい時期に相手のことを気遣うための挨拶状です。相手のことを気にかけていることが伝わるような、自分らしい言葉を入れましょう。
5.自身の近況を伝える
相手のことを尋ねると共に、自分自身について伝えることも、コミュニケーションのきっかけとなります。相手に喜ばれる寒中見舞い・余寒見舞いとなるでしょう。ただし目的やスペースの都合によっては、こちらも省略可能です。
6.今後のお付き合いをお願いする言葉
相手との関係性を円滑に保つため、重要な一文となります。「本年も変わらぬお付き合いの程、よろしくお願い申し上げます」など、定型文として頭に入れておいてください。
7.結びの挨拶
寒中見舞いや余寒見舞いを締めくくるための一文です。「この冬は例年になく寒さが厳しいようです。皆様もどうかご自愛下さいませ。」など、相手を気遣うフレーズと組み合わせるのもオススメの方法です。
8.年号と月
最後にはがきを書いた年号・月日などの情報を入れます。「平成○○年1月△日」や「平成○○年1月」など、記載することでより丁寧な印象になります。
はがきと合わせてギフトを贈ることも

一年でもっとも寒い季節に出す挨拶状だからこそ、相手を気遣う気持ちを「ギフト」で示す方も増えてきています。
年末年始の贈り物といえば、お歳暮やお年賀が一般的です。しかしさまざまな事情により、これらの贈り物ができなかった!なんてケースもあるでしょう。このような場面でも、寒中見舞いや余寒見舞いとしてギフトを贈り、日ごろの感謝の気持ちを伝えることが可能となります。
寒中見舞いや余寒見舞いでギフトを贈る際にも、マナーを守って行うことは何よりも重要なこと。特に「贈る時期」には注意してください。また挨拶状なしで、ギフトだけを送り付けるのも非常に失礼な振る舞いとなってしまいます。言葉で気持ちを伝える工夫も、忘れないようにしましょう。
さて、寒中見舞いや余寒見舞いでギフトを贈る場合には、予算の相場や品物選びで悩むケースも少なくありません。それぞれの目安や例をご紹介します。
ギフト選びの予算の相場は?
お歳暮やお年賀の代わりとして寒中見舞い・余寒見舞いのギフト選びをする場合、予算についても「同等」と考えるのが良いでしょう。相手によって幅がありますが、3,000円から5,000円程度が相場となります。
お歳暮やお年賀としての意味を含めない場合には、相手との関係性や「本当に喜んでもらえるものを」という視点で予算を決め、ギフト選びをするのがオススメです。
ギフト選び、品物で悩んだときには?
寒中見舞いや余寒見舞いで喜ばれるのは、冬の季節感を抱ける品物です。特に食べ物や飲み物系は人気が高く、相手の好みに合わせて、品物を選択するのも良いでしょう。
とはいえ、寒中見舞いや余寒見舞いとして贈る場合、年末年始の家族が集まりやすい時期をすでに通り過ぎてしまっています。「家族みんなで楽しんでもらえるもの」という視点で選ぶのも良いですが、それぞれの状況に合わせた対応を心掛けましょう。
「相手の状況がよくわからない」「相手の好みがわからずに困っている……」といった場合には、カタログギフトを選択するのもオススメです。贈る側にとっては、相場金額に合わせてカタログギフトを選ぶことができるというメリットがあります。一方受け取る側にとっては、「好きなものを選べる」というメリットがあります。
食べ物や飲み物などが掲載された一般的なカタログギフトのほか、「レストランでの食事」や「温泉入浴券」など、体験メニューが多く掲載されている体験型カタログギフトも、冬の贈り物としてもピッタリの内容と言えます。「何を選ぼうか」とワクワクする気持ちも、相手に楽しんでもらえそうですね。
寒中見舞いや余寒見舞いは、マナーを守って気持ちを届けよう
寒中見舞いや余寒見舞いは、季節の挨拶状の中でも、活用頻度が高いものだと言えるでしょう。年賀状への返礼として使ったり、喪中の挨拶状として使ったりすることができます。
はがきで行うのが一般的ですが、ギフトを贈るケースもあります。相手との関係性や自分自身の状況によっては、お歳暮やお年賀の代わりとして贈ることもできますし、相手への気遣いをきっかけに、仲を深めることもできるでしょう。
寒中見舞いや余寒見舞いは、マナーを守って行うことが大切です。特に贈る時期によっては、寒中見舞いと余寒見舞いで、名前が変わってしまうこともあるので注意してください。一年の中でももっとも寒い季節に行う挨拶だからこそ、ぜひ上手に活用してみてくださいね。