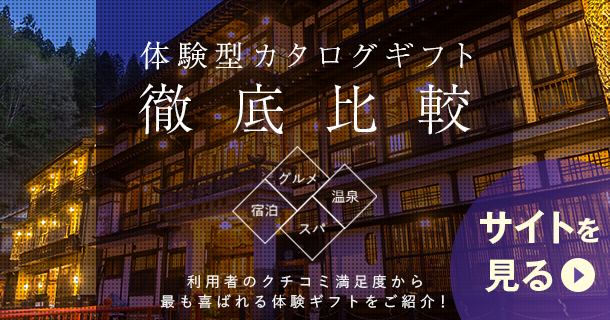お中元にカタログギフトを贈る際の注意点
普段からお世話になっている方に向けて、感謝の気持ちを込めて贈るのがお中元です。シーズンを迎えると、毎年「いったい何を贈れば良いのだろう……」と頭を悩ませる方も多いことでしょう。
また感謝の気持ちを込めて、目上の人に贈る機会も多いものだからこそ、マナーも重要! せっかくの贈り物ですから、相手への気遣いも忘れずに気持ち良くやりとりしたいところです。
お中元の選び方・贈り方における三大お悩みポイントを、それぞれわかりやすく解説していきます。「これでいいのかな……?」なんて不安を抱きつつお中元を贈るのは、もう卒業。大人らしく、堂々とお中元を贈るための基本の知識を紹介します。
贈る時期には注意

お中元を贈る際に、もっとも注意しなければならないマナーといえば「贈る時期」についてです。早く贈りすぎても、相手にとっては驚きの原因に。もちろん遅れた場合には、なんとなくモヤモヤとした気分を抱かせてしまうことでしょう。
お中元をいつ贈れば良いのかわからず、難しい!と感じてしまいがちな裏には、以下のような事情が隠されています。
・地域によってお中元を贈る時期が違う
・デパートが開催するお中元商戦の時期が、毎回違う
もっとも影響を与えているのは、やはり「地域によってお中元の時期に差がある」という点でしょう。少し前までは、以下のような区分けが一般的でした。
・関東地方 7月上旬~7月15日
・関西地方 8月上旬~8月15日
またこのほかにも、「北海道地方は7月15日~8月15日まで」や「同じ地方でも、より細かい区域によって時期が違う」などの特殊なルールが存在しています。いくつものルールが混在していることで、非常に複雑な仕組みに思えてしまうのですね。
もし、「引っ越してきたばかり」などの事情で当該地域のお中元ルールがわからないときには、身近な人に聞いたり地域の例に倣ったりするのがオススメです。慣れない環境の中でも、失礼のない振る舞いができるはずです。
また異なる地域にお住いの方に対してお中元を贈る場合には、できるだけ相手の地域の風習に合わせて贈ることをオススメします。せっかくのギフトですから、相手に気持ち良く受け取ってもらうこともマナーの一つ。受け取る側に対する心遣いの一つとして、時期の手配も慎重に行ってみてください。
さて、お中元に関するマナーで難しいと言われる「時期に関するルール」ですが、近年は少しずつ状況が変わってきています。お中元を多く扱う百貨店や大手スーパーの商戦が年々早まっていることもあり、お中元を贈る時期も早くなってきています。
関東地方であれば6月の下旬に届くようなケースもありますし、関西地方であっても、7月上旬にお中元が届くケースも少なくありません。
また、万が一「お中元の手配を忘れていて、上の時期に間に合わなかった!」なんて場合でも大丈夫です。表書きを「お中元」ではなく「暑中お見舞い・暑中御伺い」「残暑お見舞い・残暑御伺い」としてください。
8月初旬の立秋までは前者を使い、それを超えるようであれば後者を使います。目上の方に贈る場合には「御伺い」を使うのが好ましいですから、こちらもぜひチェックしてみてください。
やむを得ない事情でギフトの到着が遅れてしまった場合には、お詫びの言葉を電話や手紙で伝えるとより丁寧な印象になります。
贈るものの金額に注意

贈る時期と贈る相手を決定し、実際にギフト選びをスタートした際に、悩みがちなのが「金額」についてです。お中元売り場を覗いてみると、実にさまざまな価格帯の商品が並んでいます。
「無理のない範囲だとこのあたりだけど……相手に失礼がないようにする場合は、このあたりかも?」なんて、迷ってしまうケースも少なくありません。
お中元でもっとも大切なのは、相手に対する感謝の気持ちです。無理をして高い物を選ぶ必要はありませんし、またあまりにも高い商品を選びすぎても、かえって相手に気を使わせてしまうケースもあります。
実際に、高額なお中元が届いたあとに、「こんなに高価なものをいただいてしまって、何かお返しをしなければ!」と考える方も多くいます。かえって気を使わせてしまうことは、あまり良くありません。
お中元市場でもっとも売れている商品の価格帯は、およそ5,000円前後です。たくさんのお中元を贈る場合には、非常に大きな負担になってしまう可能性もあります。お中元は毎年続いていくお馴染みの行事でもありますから、あくまでも無理のない範囲で、気持ちを込めて贈ることを意識してみてください。
どのようなものを贈るか

最後の悩みポイントは、もっとも重要だからこそ深い悩みにもつながりやすいポイントと言えます。ずばり「いったい何を贈れば喜んでもらえるのだろう」という点です。
お中元の定番商品としては、
・洋菓子
・酒類
・そうめん
・洗剤
・加工肉の詰め合わせ
・ジュース
・コーヒー
などが挙げられます。これらのアイテムから、相手の家族構成や好みを考えた上でピッタリだと思う物を選んでみてください。
相手の家族に子どもがいるなら、洋菓子やジュースなどは非常に喜ばれるでしょう。一方でお酒が好きな方に対しては、好きな銘柄のお酒を贈るのがベストです。毎年の「定番品」を決めている場合には、相手方もそれを期待していることも考えられます。伝統を守るのも良いでしょう。
どうしても相手の趣味がわからない……という場合には、日持ちがするそうめんや、使われる機会が多い洗剤などを選ぶのもオススメの方法です。「もらって困る」なんて、最悪の事態は避けられるはずです。
とはいえ、お中元は「贈る時期」が決められていることもあり、「いくつものギフトを同時にいただく」なんてケースも多くあります。同じような商品がかぶってしまうと、やはり少し残念な気持ちを抱いてしまうものかもしれませんね。
こんなときにも対応しやすい品物として、近年人気を集めているのが「カタログギフト」です。少し前までは「引き出物」や「内祝い」というイメージも強かったカタログギフトですが、近年では「お中元」として活用する方も増えてきています。
お中元にカタログギフトを選択するメリットとしては、以下のようなポイントが挙げられます。
・贈る側の手間が軽減できる
・贈られた側が自分で好きなものを選択できる
・ギフトをもらう時期を調整できる
カタログギフトであれば、「全員に同じ物」を贈ったとしても、その中身はそれぞれでバラバラになります。相手にとって、本当に必要なものを贈ることができるでしょう。
また食品などでは、「せっかくいただいたものの、消費期限が気になる」なんてケースも少なくありません。カタログギフトにも食品は掲載されていますが、「申し込みをして実際に届けてもらう時期」については、ある程度自分で調整することが可能です。
「今度みんなで集まるときに、ちょっといいお肉を……」なんて注文することもできますから、非常に使い勝手が良いと言えるでしょう。
お中元としてのカタログギフトは、実は人気が高い
カタログギフトならではのメリットを聞いても、「お中元にカタログギフトを贈るのは、なんとなく味気ない気がする……」なんて悩む方も多いのかもしれませんね。相手のために心を込めて選ぶことが、お中元を贈る意義でもあります。カタログギフトでは「相手に選んでもらう」ことになりますから、なんとなく「手抜き」のように思えてしまうのかもしれません。
しかし実際に、お中元としてカタログギフトをもらうと「嬉しい」という方は非常に多くいます。家族の嗜好に合わないものをもらっても、ただただ困ってしまうだけ。そこに相手の気持ちがこもっているからこそ、微妙な気持ちを抱いてしまう方もいます。
カタログギフトの場合は、カタログに掲載されている商品から相手の好きなものを選んでもらうスタイルとなります。大切なのは、「相手が喜んでくれそうなものが多数掲載されている、質の高いカタログギフトを贈る」ということです。
「カタログギフトならどれでもいい!」と考えるのではなく、「本当の意味で相手に喜んでもらえるカタログギフトを」という視線で選べば、心のこもった素敵なギフトになるでしょう。